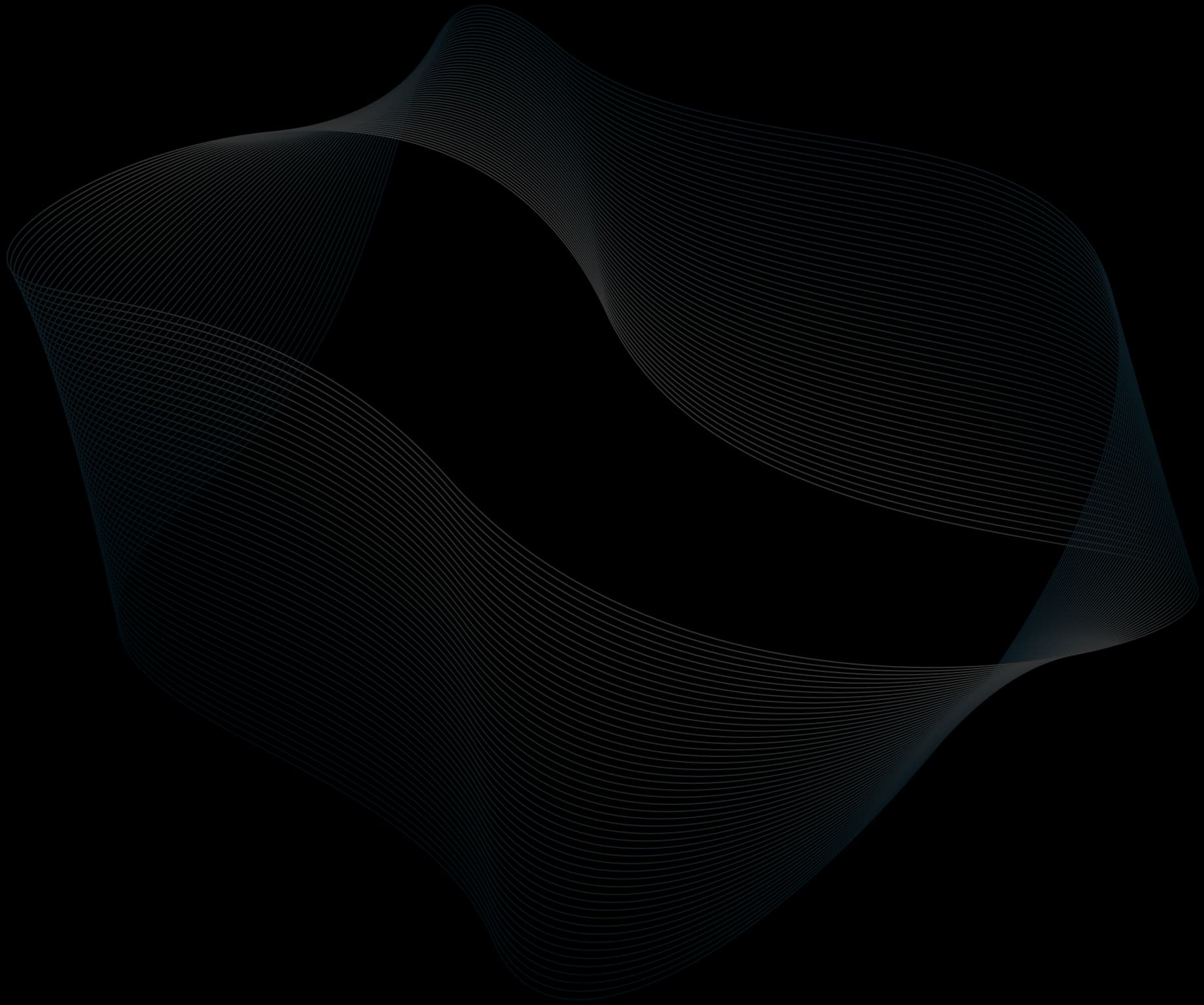
赤字案件の根本原因は“属人提案”──SIer営業を利益体質に変える再現設計とは?
この記事の要約
-
「受注が増えても利益が残らない」──SIerに広がる“見えない赤字案件”の正体とは?
-
その原因は提案の属人化にあり。情報の点在・曖昧な見積・判断のブラックボックス化が赤字を招く構造を解説。
-
組織で安定して利益を出すには、営業プロセスの“再現設計”が不可欠。具体的な3ステップで体系的に整理。
-
従業員10万人超のSIer事例では、再現設計によりアポイント数が1.56倍に改善。属人依存から脱却。
-
属人性から抜け出し、組織で利益を生む営業体質へ──いま経営が踏み出すべき一手とは。
目次
- 1. はじめに──SIerに広がる「見えない赤字案件」の実態
- 2. 属人提案が赤字を生む構造──点在・曖昧・継承不能な“情報の壁”
- 情報の「点在」と「漏れ」がコストを生む
- 見積の精度がブラックボックス化
- 3. なぜ属人提案が、組織の利益を蝕むのか?
- ■提案内容・価格のブレによる粗利の不安定化
- ■商談判断の属人化による機会損失
- ■若手育成の停滞と人材コストの増大
- 4. 利益体質を実現する“営業再現設計”のアプローチ
- ステップ①:接点情報の一元化と自動記録
- ステップ②:トップ営業の思考をテンプレート化
- ステップ③:AIが「次の一手」を提示する
- 5. 実践事例──あるSIer企業が“再現設計”で変わったこと
- 6. まとめ──赤字案件を止める鍵は「再現性」にある
1. はじめに──SIerに広がる「見えない赤字案件」の実態
「受注数は増えている。だが、利益が残らない」。 このような声を、SIer(システムインテグレーター)の経営層から耳にすることが増えてきた。
一見、案件が増え、売上も立っているように見える。しかし蓋を開けてみると、期末になると粗利が削られ、「帳尻合わせの残業」が常態化。ときには、プロジェクトが終わってみて初めて赤字が判明することすらある。
こうした“見えない赤字案件”の根本原因は、単なる価格交渉力の不足や、追加要件の頻発ではない。 多くのケースでは、提案プロセスが属人化していること、すなわち「営業やSE個人の勘や経験」に依存した非構造的な提案体制こそが、赤字を生み出す出発点となっている。
本稿では、属人提案がもたらす構造課題と経営インパクトを明らかにし、再現性ある営業設計による利益体質への転換方法を、実践ステップと事例を交えて解説する。
2. 属人提案が赤字を生む構造──点在・曖昧・継承不能な“情報の壁”
情報の「点在」と「漏れ」がコストを生む
提案フェーズでは、顧客とのやりとりが多くのチャネルで発生する。要件定義ミーティング、チャット、メール、電話、共有資料──しかしこれらの情報は、多くの場合、営業個人のノートPC、ローカルフォルダ、頭の中に閉じ込められている。
録音データが残っていても、要点やリスクメモは担当者の感覚に依存し、プロジェクトチーム全体で共有されていない。こうして提案内容に曖昧さが残ったまま進行し、後になって「そんな話は聞いていない」「そこまでやる想定ではなかった」という認識のズレが発生。追加工数を無償で背負い込む構図が常態化する。
見積の精度がブラックボックス化
IPAの調査によれば、ソフトウェア開発プロジェクトにおいて「見積工数と実績工数の乖離が20%以上」と回答した企業は46.3%。その大きな要因は、提案段階でのヒアリング漏れと、根拠の曖昧な見積設計である。
例えば、顧客の本音や制約条件、期待値など、議事録に書きづらい“暗黙情報”は担当者の頭の中にしか存在しない。これが組織的な判断やレビューに反映されず、リスクや追加工数が見落とされたまま見積が確定されてしまう。
参考資料:2025年からの営業DX|勝てる組織を創る自動記録ツール選定
3. なぜ属人提案が、組織の利益を蝕むのか?
属人化の恐ろしさは、「目の前の案件は回っているように見える」ため、緊急性のある課題として見過ごされやすい点にある。
しかし実際には、以下のような深刻な経営インパクトを引き起こしている。
■提案内容・価格のブレによる粗利の不安定化
価格設計、提案スコープ、運用範囲などが担当者ごとに異なると、粗利にばらつきが生じる。たとえば、営業が「安くしてでも取りたい」と価格を独断で下げてしまえば、経営が描く収益計画との乖離が広がる。属人的な判断が、企業全体の利益構造を脅かすのだ。
■商談判断の属人化による機会損失
どの顧客に、どのタイミングで、何を提案すべきか──この判断が営業個人に委ねられていると、大型案件でも「提案の出し遅れ」「放置による失注」といった機会損失が発生する。こうした見えにくい損失は、結果が出るまで顕在化しないため、組織として対応しづらい。
■若手育成の停滞と人材コストの増大
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)に依存した育成スタイルが依然として主流であり、営業やプリセールスが一人前になるまでに数年を要するケースも多い。トップ営業の“暗黙知”が形式知化されておらず、「見て覚えろ」「同行して盗め」という再現性に乏しい体制が、新人の即戦力化を阻んでいる。
4. 利益体質を実現する“営業再現設計”のアプローチ
属人提案を解消するには、単なる「標準化」では不十分だ。目指すべきは、誰が担当しても同じ品質で商談・提案・見積ができる状態=再現設計である。
そのために必要な3ステップは以下の通りである。
ステップ①:接点情報の一元化と自動記録
- ZoomやTeamsでの打ち合わせを自動で録音・文字起こし
- 顧客名やプロジェクト単位で自動紐付けし、情報を構造化
- 営業・SE間でリアルタイムにリスクや要点を共有
ステップ②:トップ営業の思考をテンプレート化
- 過去の受注/失注データをAIが解析し、勝ちパターンを抽出
- 「この業種・この条件なら、こう聞け」「この要件にはこの工数」といった提案テンプレートを整備
- 属人化していた“提案の型”をナレッジとして組織に蓄積
ステップ③:AIが「次の一手」を提示する
- 商談ログをもとに、AIが「次に打つべきアクション」を提示
- たとえば「この案件では追加要望が出やすい」「次回のレビューは○日後が適切」など、意思決定支援を自動化
- 若手でも判断を誤らず、商談を前進させられるようになる
5. 実践事例──あるSIer企業が“再現設計”で変わったこと
従業員10万人超の大手SIer・A社。新規顧客の開拓に向けてSalesforceを導入し、営業活動の効率化と可視化に取り組んでいたものの、営業活動量は伸び悩み、それに伴いアポイント数も目標に届かない状況が続いていた。
現場では「成果に繋がるアクションが再現されていない」という課題感が共有されていた。
同社は以下のようなステップで、営業活動の再現設計に取り組んだ。
- アクションを定量化:商談前後の行動ログを記録・分析し、現場で繰り返されている営業アクションを定量的に可視化。
- 営業アプローチを型化:高い成果を出している営業のアプローチをテンプレート化し、チーム全体に展開。
- Playbookによる業務効率化:ワークフローによるメールの自動化と、チャネルごとの最適な使い分けを仕組み化。
無料資料:AI営業支援ツール10選:効率化と成果向上を実現する選び方と活用法](https://magicmoment.jp/blog/10-recommended-ai-sale-tools)
成果(導入から1ヶ月で定量改善):
- 月間アクション数:35件 → 44件に増加
- 月間新規アポイント数:16件 → 25件に増加(1.56倍)
- 活動の自動化と型化により、行動量の増加だけでなく、トップパフォーマーと同等の質の高い営業オペレーションが、チーム全体で再現されるようになった。
6. まとめ──赤字案件を止める鍵は「再現性」にある
属人的な提案によって生じる赤字案件は、現場だけの問題ではなく、企業の収益構造そのものに影を落とす経営課題である。 特定の個人に依存した体制では、どれだけ人を増やしても利益は安定せず、属人性の積み重ねが組織全体の足かせになる。
赤字案件は、提案段階での曖昧な情報や属人的な判断によって、商談が始まった瞬間に構造的に生まれている。だからこそ、属人性を前提とした営業体制を見直し、「情報が残り、学び、活かされる」再現性ある提案設計を、経営の意思として整備することが不可欠だ。利益を生み出す営業は、“人”ではなく“仕組み”で育てる時代。いまこそ、その第一歩を踏み出すときである。
Magic Moment Playbook 無料製品資料の問い合わせはこちら
入力のいらないCRM Magic Moment Playbook の詳細資料を入手
Magic Moment Playbook の詳細について資料でご確認いただけます
**【資料請求】 Magic Moment Playbookの詳細な機能や導入事例、料金プランをまとめた資料をご用意しています。具体的な機能や効果をご確認ください。【個別デモンストレーション】 貴社の具体的な課題や状況に合わせて、Magic Moment Playbookがどのように貢献できるか、30分のオンラインデモで体験いただけます。自社データでの自動入力体験もご相談ください。【お問い合わせ・ご相談】** 導入に関するご不明点や、SaaSビジネスにおけるデータ活用のお悩みなど、お気軽にご相談ください。
入力のいらないCRM Magic Moment Playbook の詳細資料を入手
Magic Moment Playbook の詳細について資料でご確認いただけます
